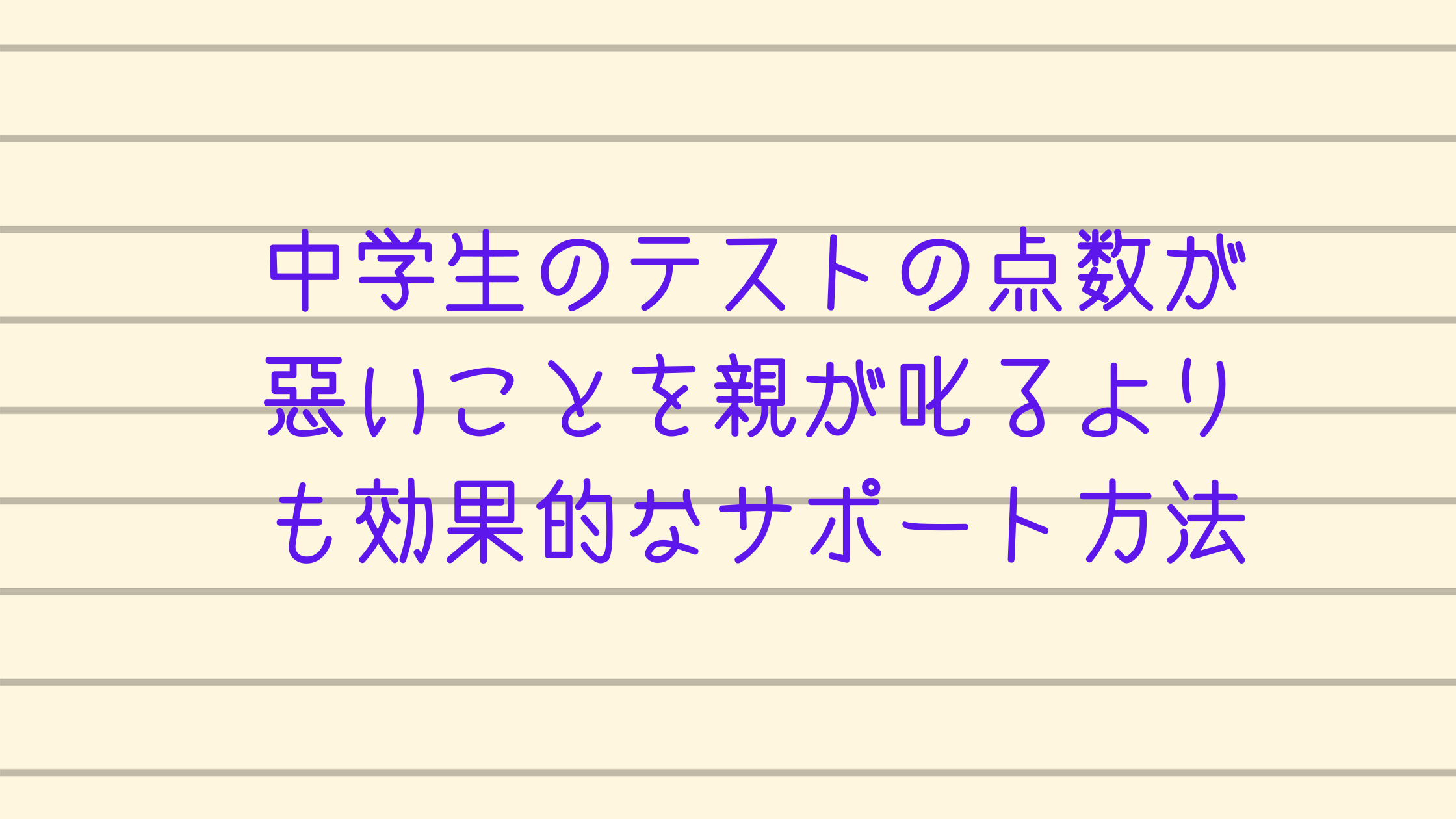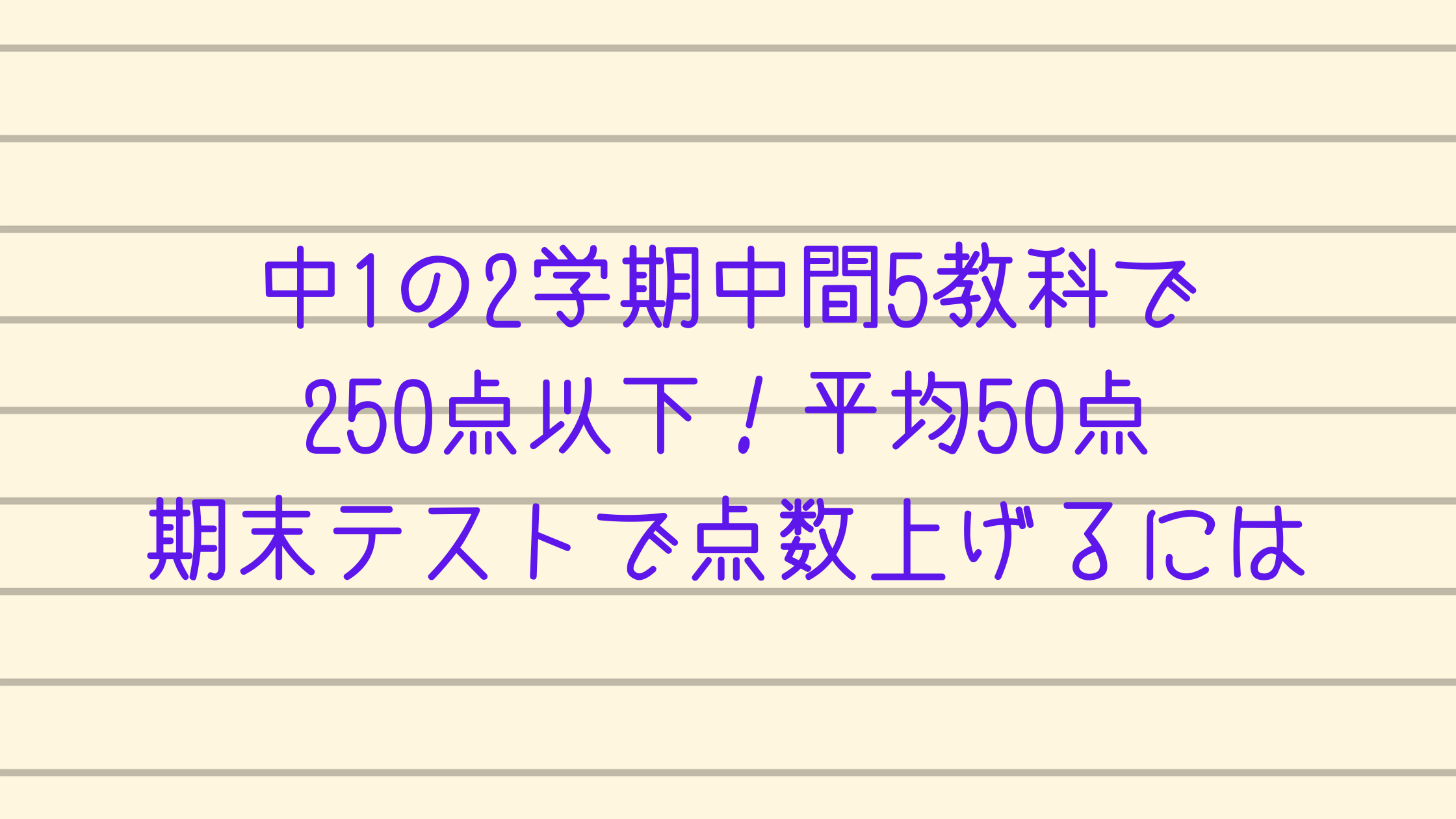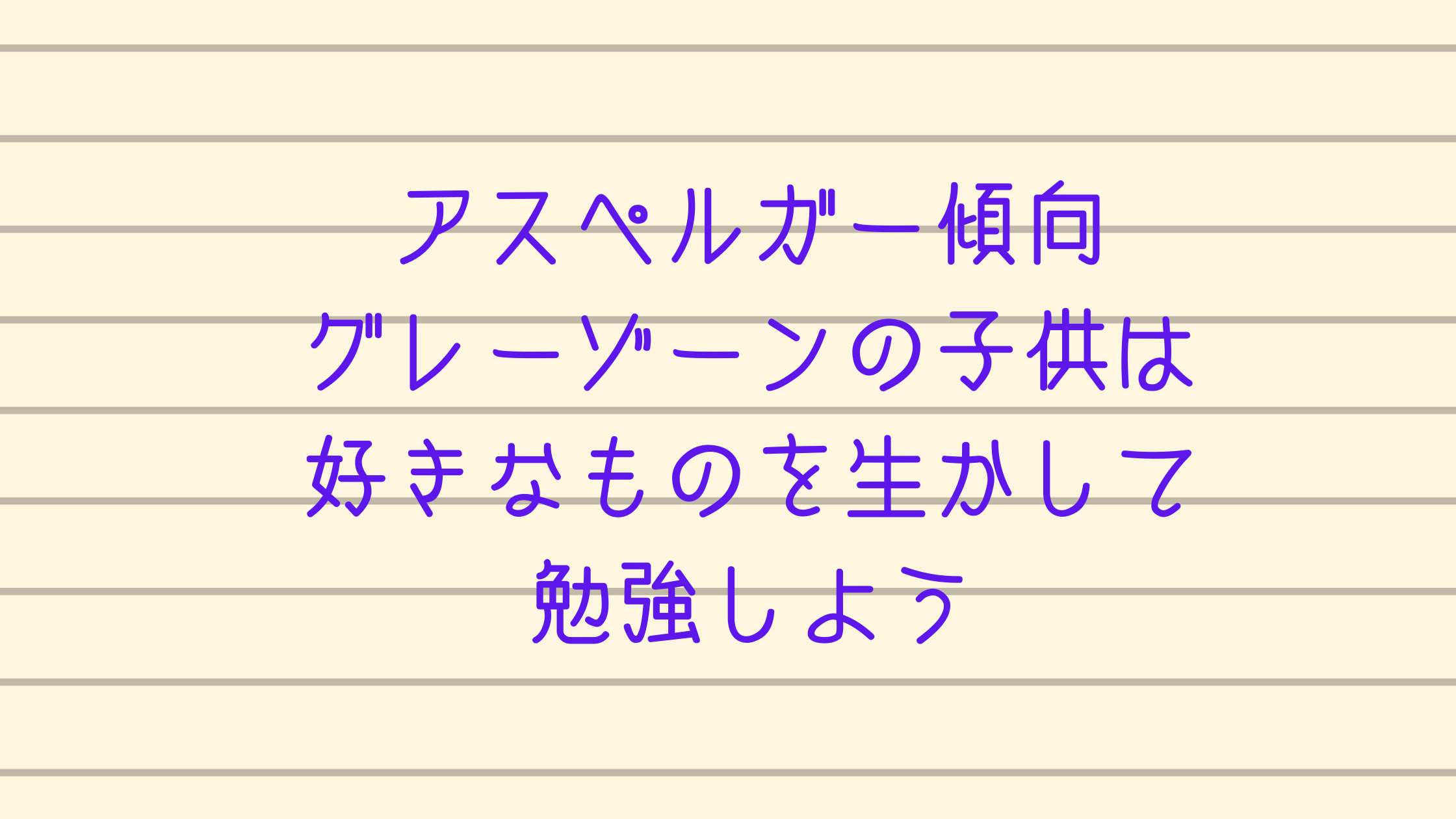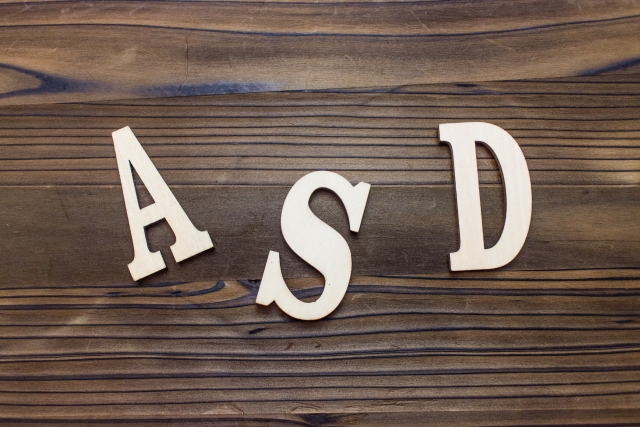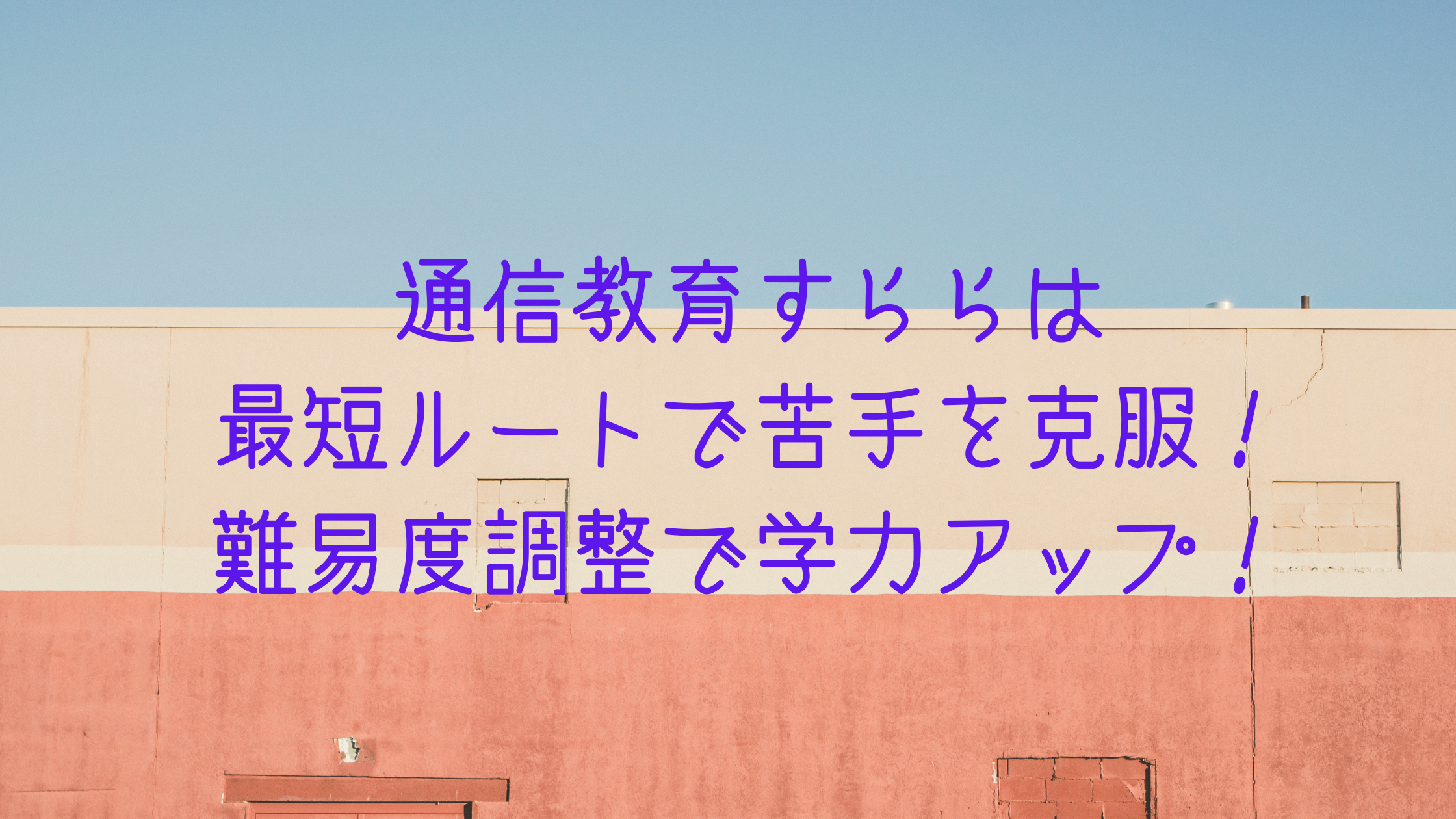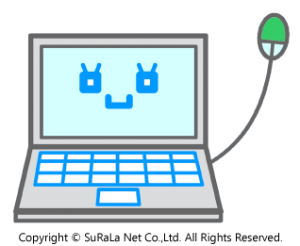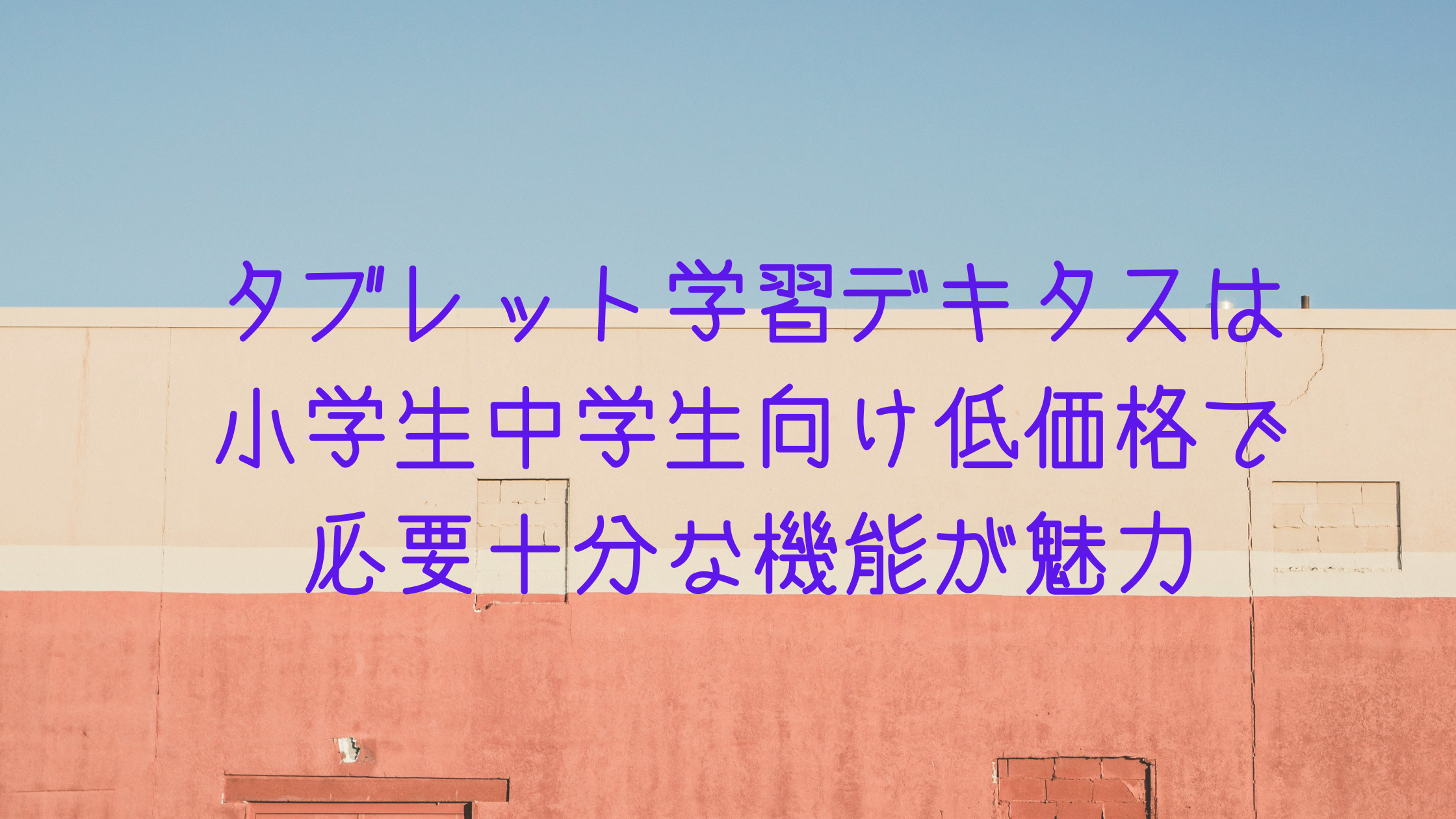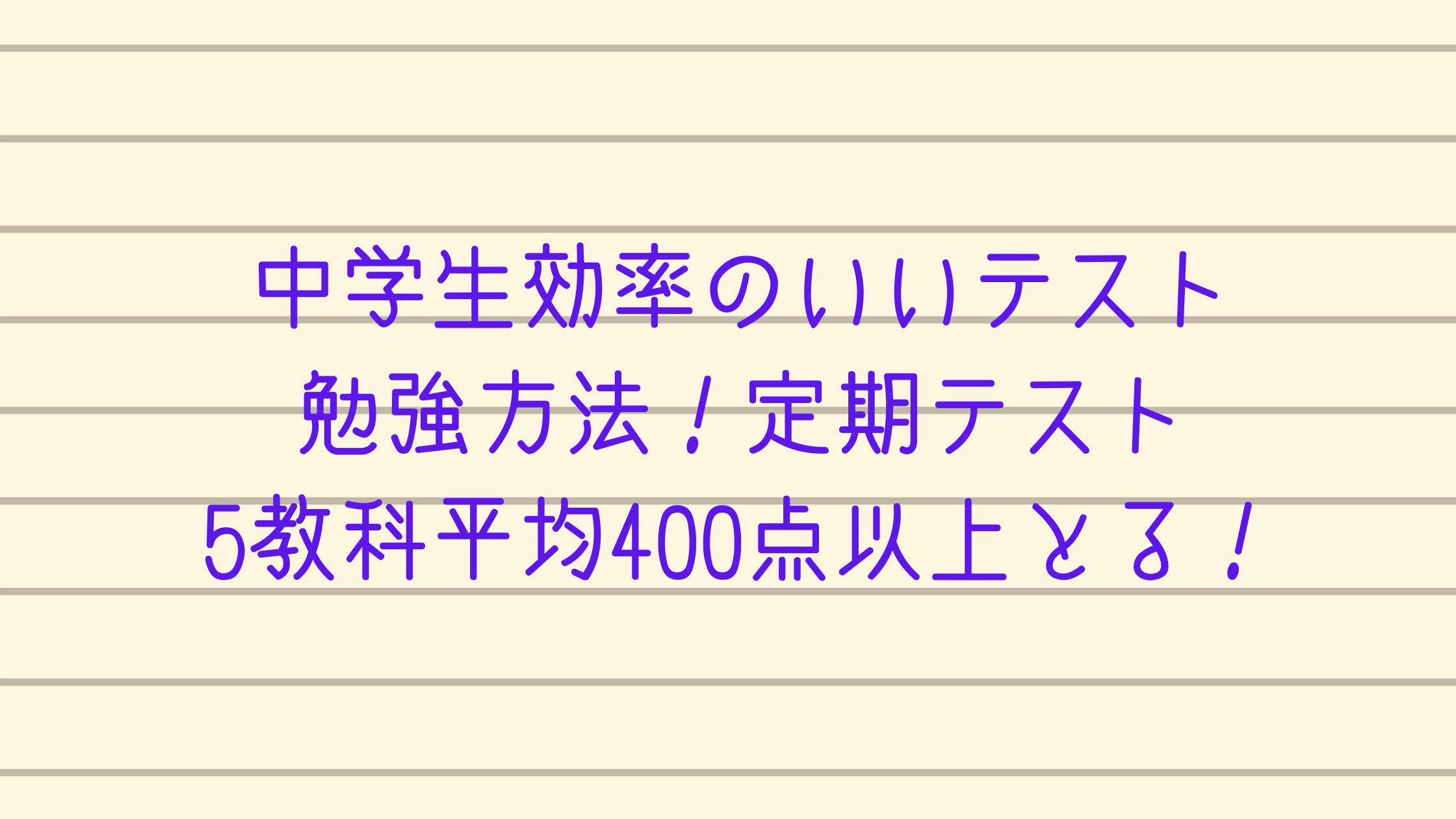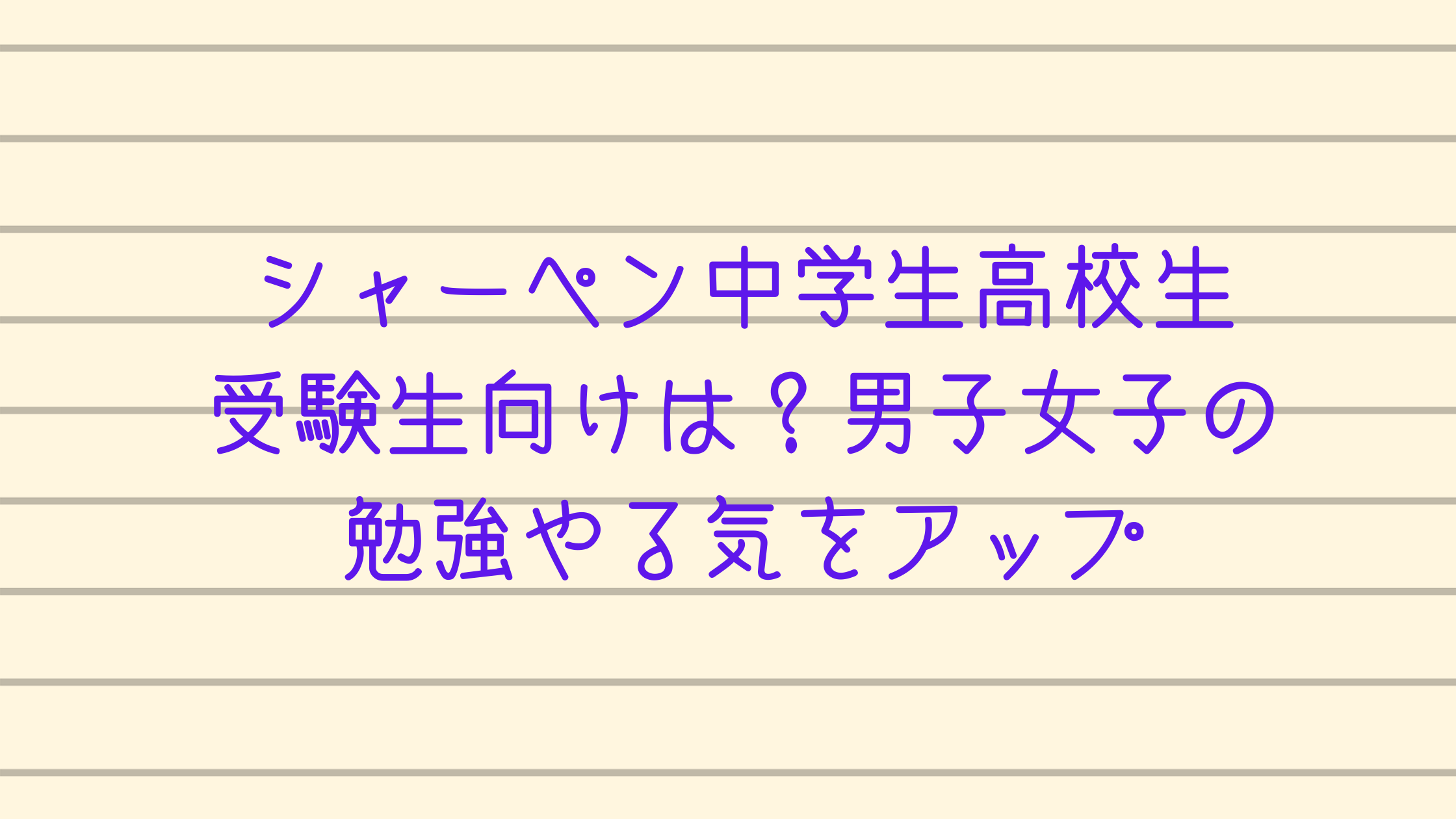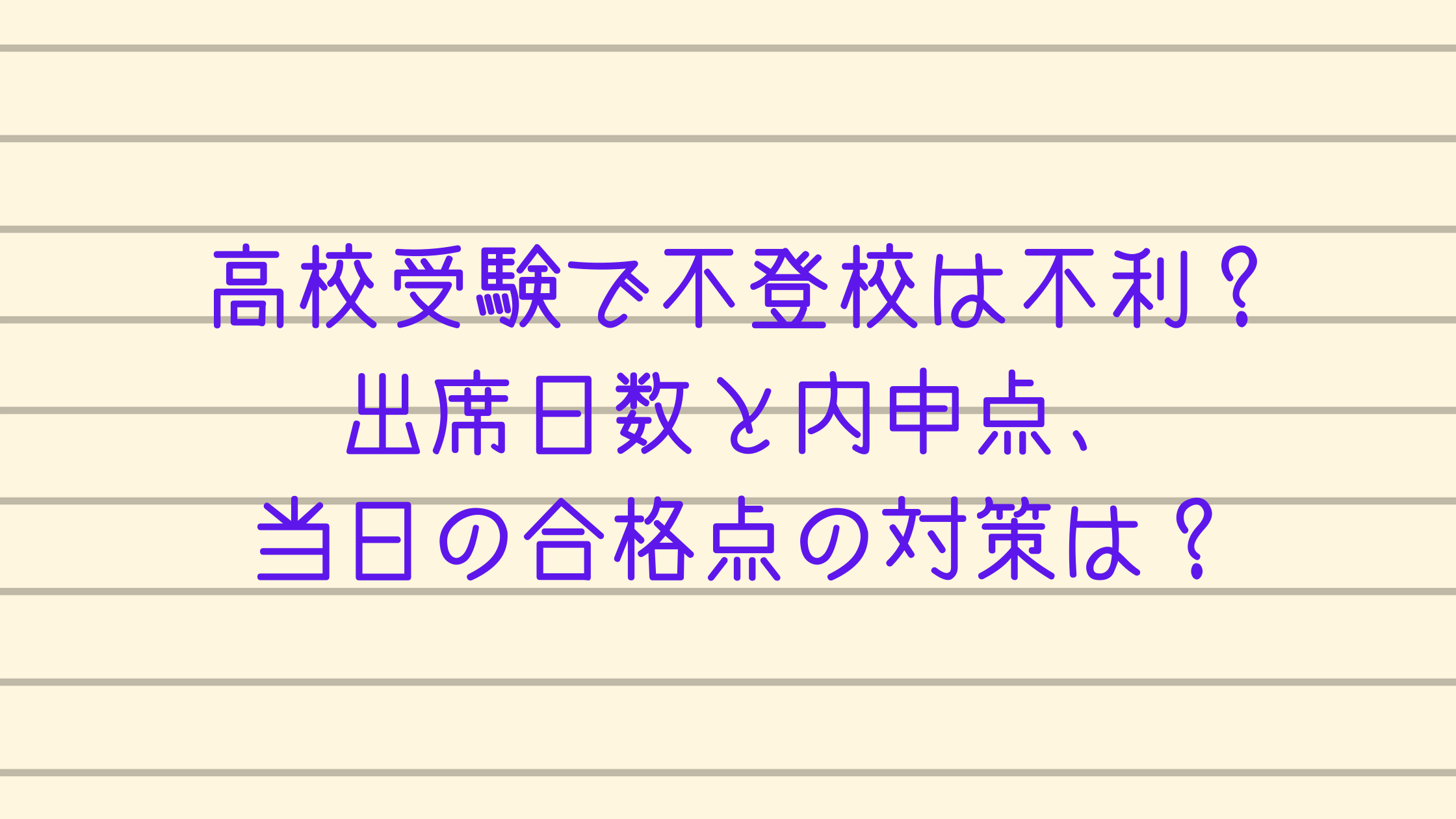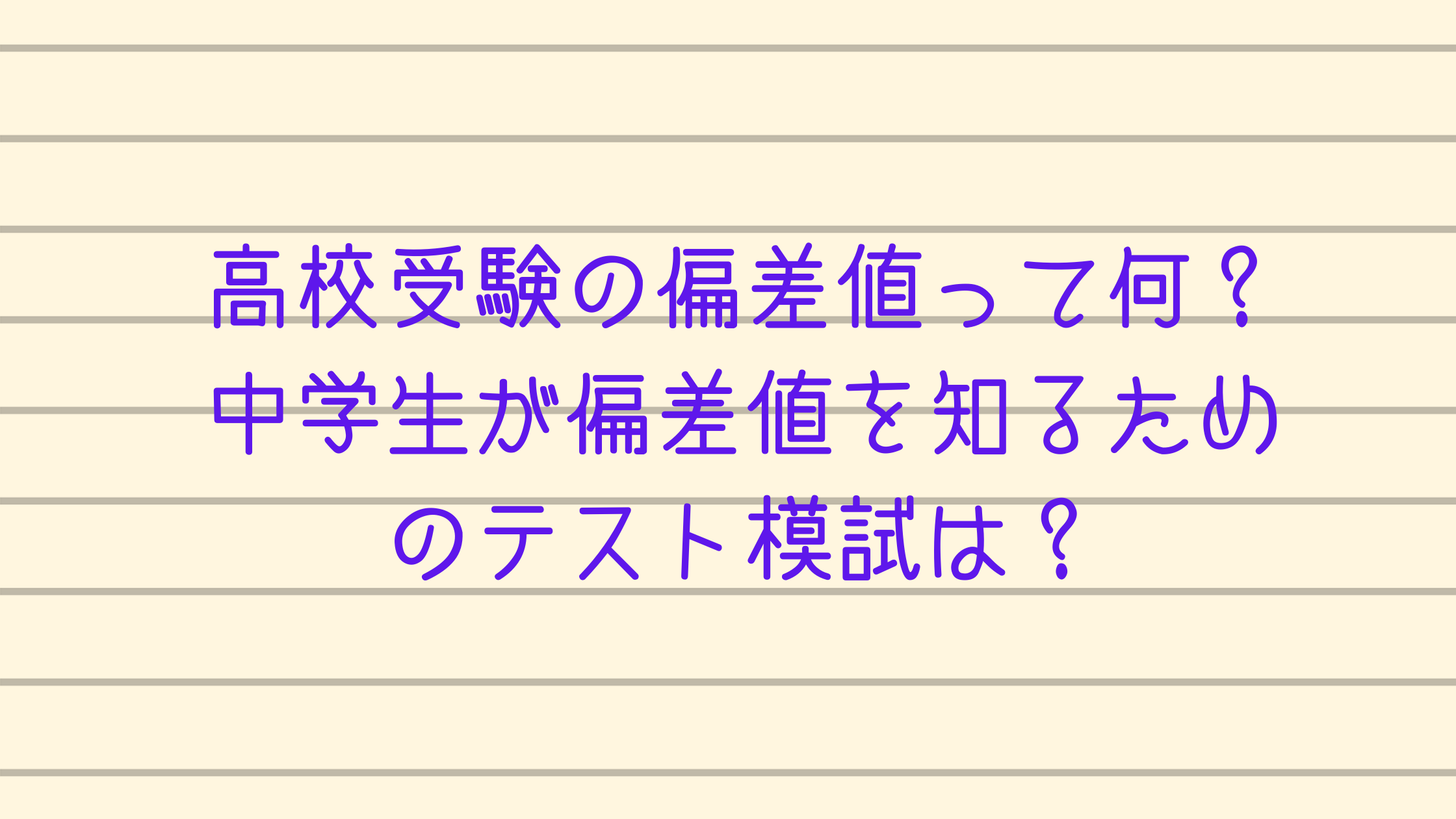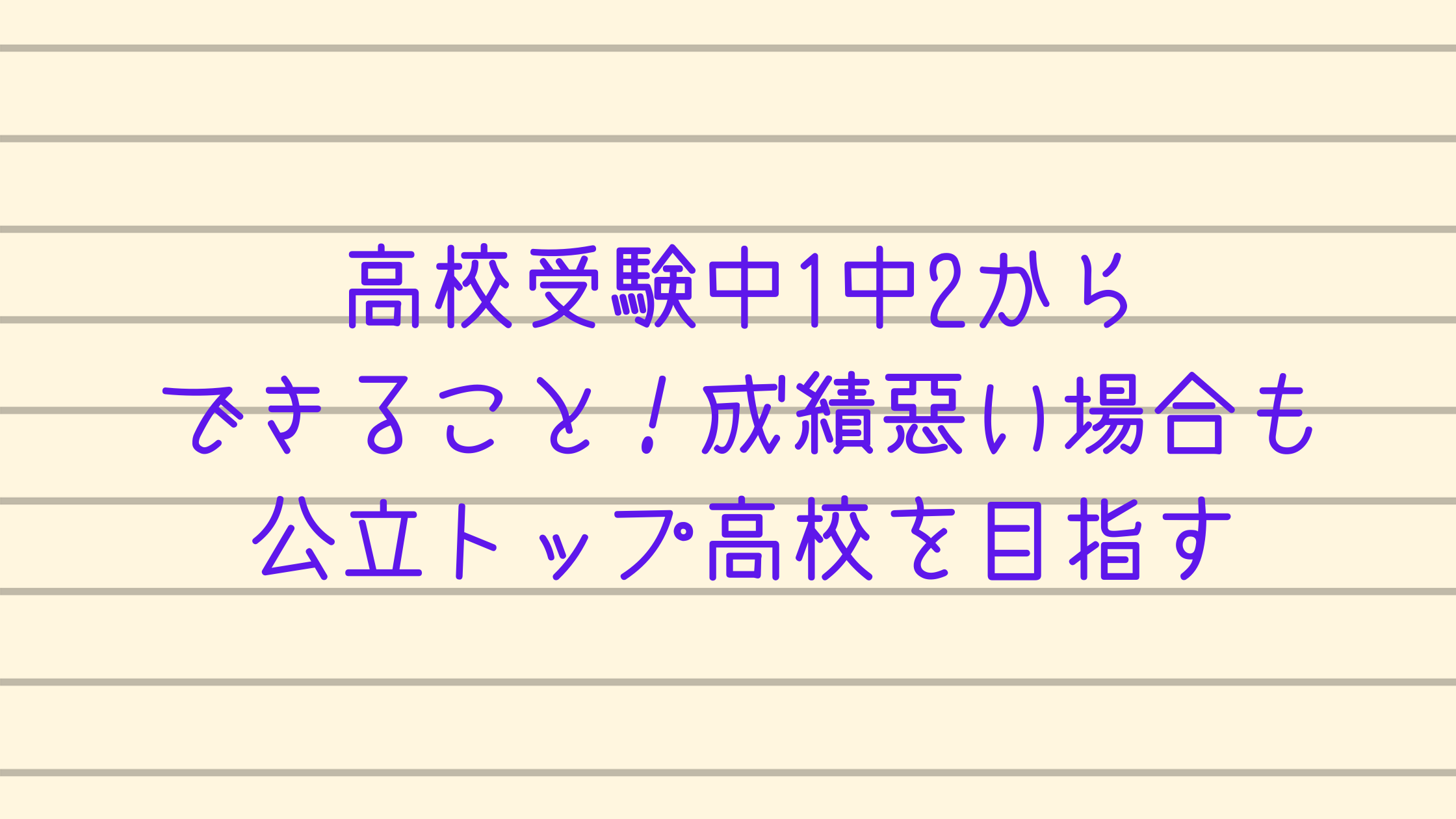中学生の保護者
「テストの点数が悪いとつい叱ってしまうが、
子どもはやる気を出してくれない。
どうしたら点数がアップするのか知りたい」
中間期末の定期テスト、実力テスト、模試など、テストの結果が戻ってくるのは、お子さん本人だけでなく、親、保護者の皆さんもどきどきしますよね。
良い成績をキープできていたり、前回よりも上がっていたりしたら、自然に褒め言葉が出てきますが、
よくない結果が戻ってきたときについ叱ったり、
小言をいったり
することもあるのではないでしょうか。
その次によい結果を出すために、
悪かったときに親がどう対処するか、
考えてみることも大事だと思います。
この記事を読めば、子どもがテストで悪い点を取って返ってきたときの親の心の持ち方がわかります。
テストの点数が悪い時親が叱るよりもよりそってあげる
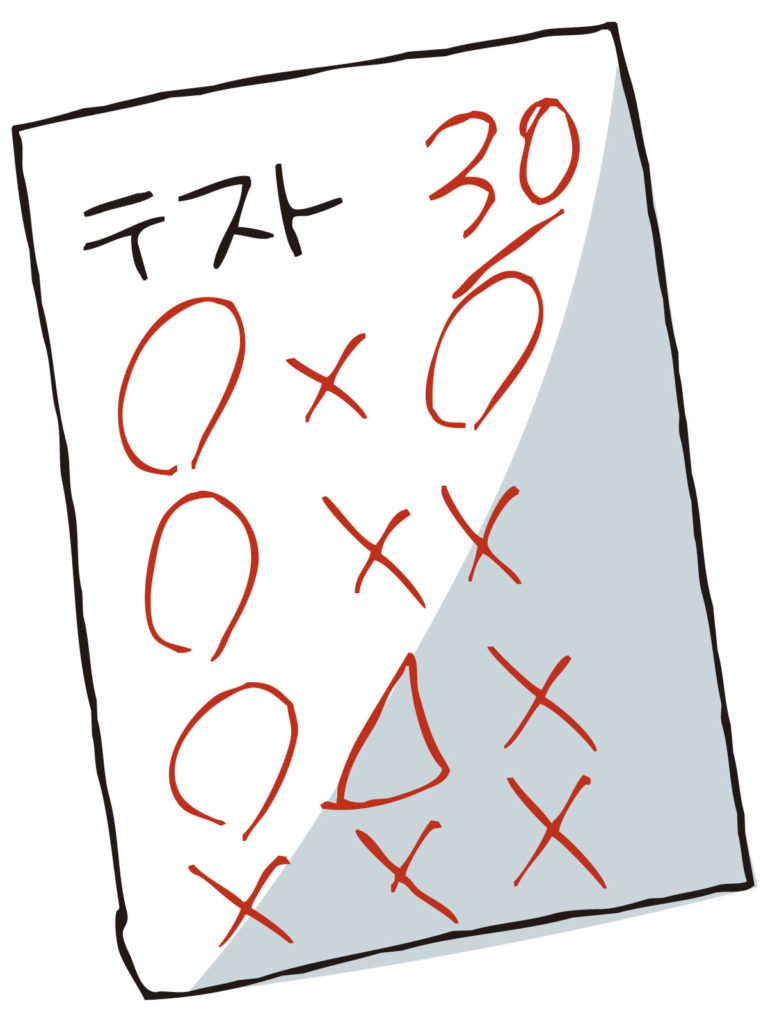
テストの点数が悪かったときに、親としては、
「勉強していなかったから」と
お子さん本人を責めたり批難したりする気持ちが起きることが多い
と思います。
・ゲームやテレビ、スマホでラインやYouTubeなどにふける。
・お友達と遊んだりばかりしている姿が目に付く。
・部活が忙しすぎて部活以外の勉強に全く時間を使えない。
というパターンもあるでしょう。
楽な方へ流されやすい態度や
授業態度提出物への姿勢もいいかげんな面が目に付く
かもしれません。
もしくはお子さんなりに努力して勉強している割に、
成績が伸びない、悪いなどの悩みがある場合もあると思います。
いずれの場合も、お子さんに合う勉強法が見つかっていないということが原因であることが多いと思います。
なので、お子さんがやってない、やり方が悪いなど小言を言うよりは、
お子さんに合う方法を一緒に探そう
とよりそってあげるほうが次につながりやすいです。
くどくどお説教をするのはお子さんの耳に入らないことが多いと思います。
また、親子だけに言葉に遠慮が無くなって、
むき出しの感情をぶつけ合うことにもなりがち
ですので、お互いが傷つくケンカにならないように、親が注意する必要があると思います。
成績が悪い場合について詳しくはこちらの記事も参考にしてください。↓
通知表が下がった!1や2の最悪な内申…中学生の親は先生へ相談?
中1の三者面談で保護者が先生に聞くこと話すこと!成績悪い場合改善するには
高校受験3ヶ月で偏差値10上げる?半年で偏差値20上げる方法はある?
中学生テスト点数が悪いときは言い訳もきいてあげよう
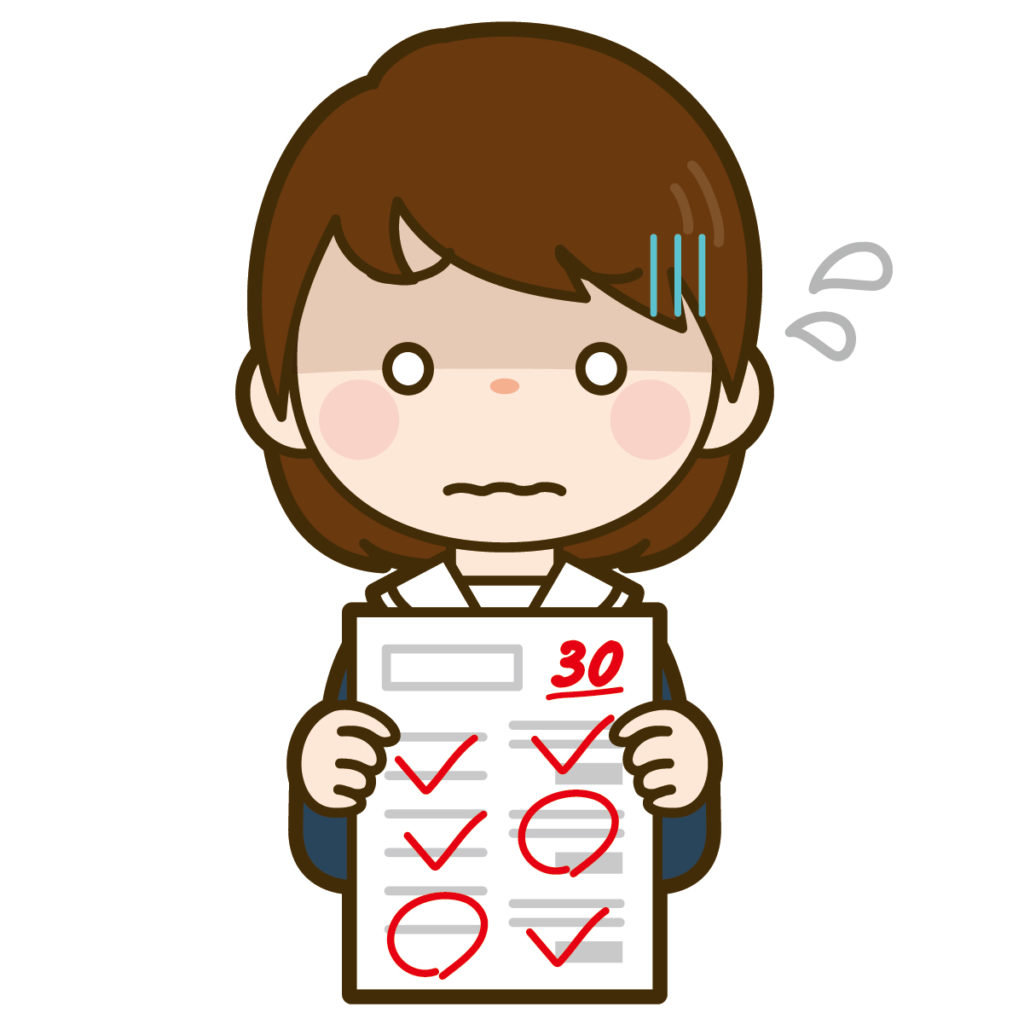
中学生のお子さんで、テストの点数が悪かったときに、
適当な言い訳をして、
あまり点数を気にしていないようにみえる
お子さんもいらっしゃると思いますが、多くの場合、
実は内心落ち込み、とても気にしていると思います。
中学の頃、娘が良く言っていましたが、テストが返却されると、お友達が口々に親に見せたくない、怒られる、塾に行かされると嘆き始めるのだそうです。
勉強できない自分のことをあまり考えないようにしているので、
反抗期もあいまっていっけんふてぶてしく怠けているようにみえてしまう
ことが少なくないと思うのです。
できない自分になげやりになって絶望しているのかもしれません。
言い訳も少しは聞いてあげましょう。
なので、自分に合った勉強のやり方が身について、成績が実際に上がり始めると、
おそらく表情や態度によろこびや自分への自信が表れてくるでしょうし、実際そういうお子さんは多いと思います。
子供の反抗期についてはこちらの記事でも詳しく書いています。↓
反抗期の勉強のさせ方は?子供の感情やストレスに注目した親の接し方
テストが悪かった時は親子で気持ちを切り替える

テストが悪かったときには、親は気持ちを切り替えて、
できたところだけほめて、あとはたんたんと簡単に見直しをするようにいっておく
のがよいです。
そして、お子さんに合う勉強法を探してあげるのが良いと思います。
塾や通信教育をすでにご利用かもしれませんが、成績が上がらない、下がっているなどの場合は、別の方法を探すのが良いと思います。
自宅学習教材ですららというインターネット塾が最近注目されているのですが、無学年制で必要なところから学び始めることができます。
[ad_tag id=”2131″]
勉強が苦手、いままで塾や通信教材でうまくいかなかった、などのお子さんにぜひおためしいただきたい学習教材です。
パソコンやタブレットを使って学習します。
学力診断テストで、お子さんの学習のヌケモレをチェックし、どこをどう勉強したらいいのかひとめでわかるようになっている教材なのです。
お子さんに必要なところを学習していくので、時間の無駄がなく無理なく短時間でも効果的な学習ができるのが魅力です。
それぞれのお子さんの間違え方を分析し、苦手つぶしに最適な問題が自動で出題される画期的なシステムです。
苦手な単元は前の学年から、得意な単元は好きなだけ先取りをしてもかかる費用は同じなので経済的ですね。
復習や予習に【当たり】のテキストを見つけるまで教材を買いこむより断然お得に学習が出来ます。
すららコーチというプロの塾講師のフォローも料金に含まれていて、お子さんに合わせた学習計画を立ててくれます。
すららコーチは保護者向けの情報提供、フォローもしてくれるので、親子で学習状況をお互い把握できて、プラスの声掛けを増やすことができるようになっています。
すららについては以下の記事でも詳しく書いています。↓
勉強が苦手な子ども向け小学生中学生通信教育ランキング!すららがおすすめ!
まとめ
テストが悪かったときには、親は気持ちを切り替えて、できたところだけほめて、あとはたんたんと簡単に見直しをするようにいっておくのがよいです。
そして、お子さんに合う勉強法を探してあげるのが良いと思います。
すららは、勉強が苦手、いままで塾や通信教材でうまくいかなかった、などのお子さんにぜひおためしいただきたい学習教材です。
すららは公式サイトから無料体験できるので、ぜひお試しになってみてください。↓
[ad_tag id=”2032″]