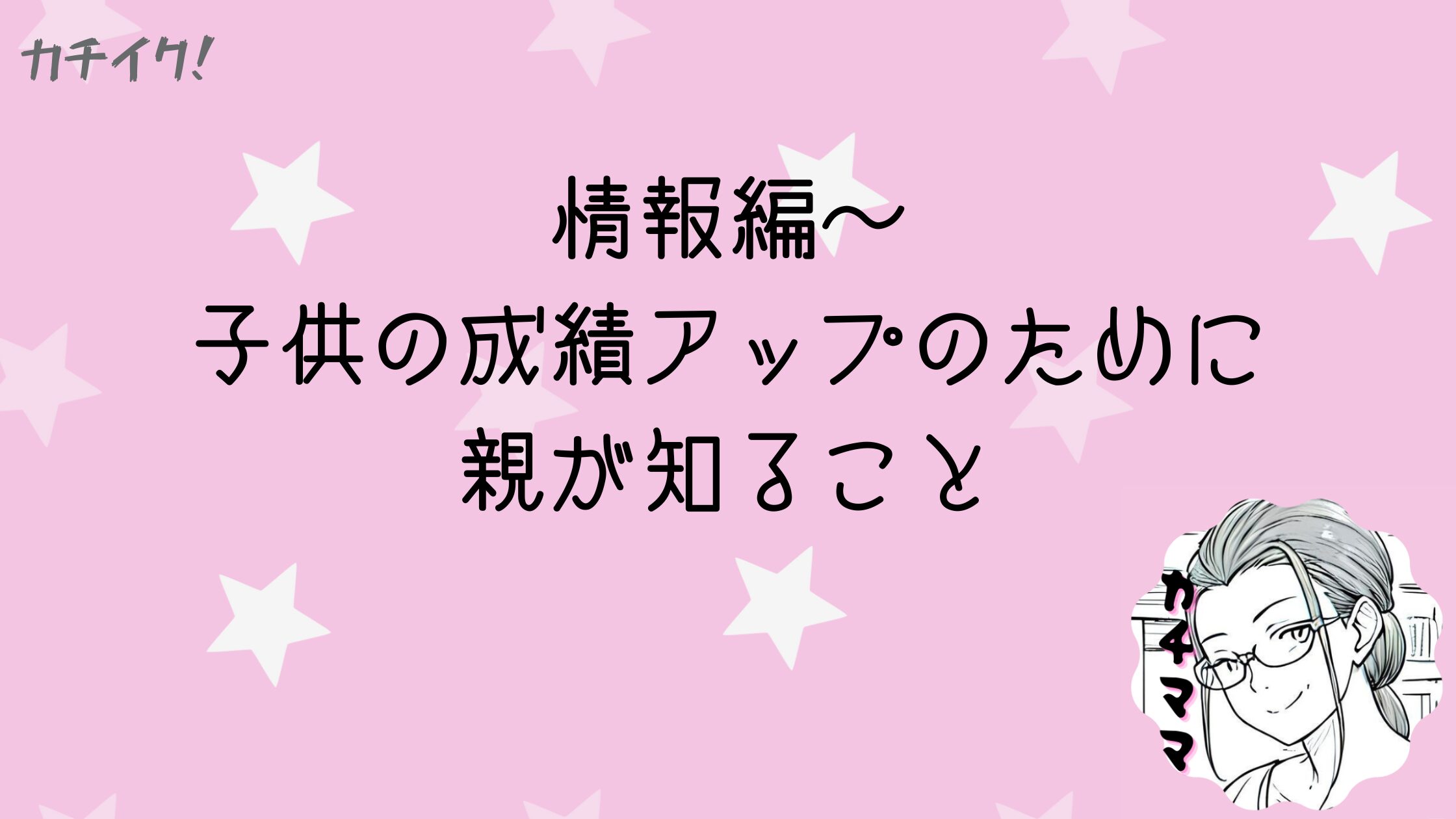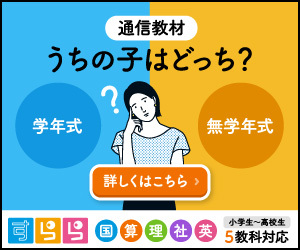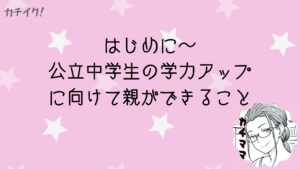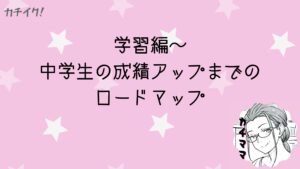このサイトは
学習編~中学生の成績アップまでのロードマップ
情報編~子供の成績アップのために親が知ること
受験編~高校入学までに親がすること
に分かれています。
それぞれ並行して進めていくイメージで読んでください。
このページでは、情報編~子供の成績アップのために親が知ることについて説明します。
中学生の成績アップのために親が知ること
親が一度に何もかも子供や子供を取り巻く環境について知るのは難しいので、普段から意識して、だんだん情報を得ていくのがおすすめです。
情報編~子供の成績アップのために親が知ること
【1】子供を知る、親が自分を知る
【2】学校を知る
【3】子供の学力を知る
【4】高校について知る
【5】入試 受験状況を知る
【6】塾、通信教育、家庭教師など学習サービスを知る
【1】子供を知る、親が自分を知る
親が子供について知っておくとよい5ポイントをあげてみました。↓
1◎どんな子供か
性格・特徴・強み・弱み
2◎子供の好きなこと楽しむこと欲しいもの
食べ物・レジャー・趣味・スポーツ・ゲーム・動画・部活・友人
3◎子供の家庭での様子
親家族との関係・生活ルーティン・悩み・イヤなこと
4◎子供の学校での様子
・友だち先生との関係
・授業、行事での態度
・子供の学力勉強の得意不得意
・悩み イヤなこと
5◎子供の夢 将来への希望 関心
憧れの職業・興味のある高校大学・夢見ている生活
親が自分の子供のころを振り返って自分の気持ちや考えていたことを思い出したりして、子供の今の気持ちを想像してみるのも良いですね。自分が子供のころ親のかかわり方でうれしかったこと、いやだったことを思い出すのも参考になります。自分がどんな親なのかを振り返り自分を知る時間も大事です。
【2】学校を知る 学校の方針、先生、友達、カリキュラム、学習進度、部活、行事など
親が、学校生活や学習内容を把握し、学校や先生の良い面を見て基本的に信頼するのはとても大切と思います。
習い事や塾、部活なども同様です。
なので、親は、子供からの先生についての言動をよく聞いておき、行事や参観、面談などの機会にもできるだけ先生に接して、先生の良い面を知るようにしましょう。
(※逆に心配な面なども注意して見聞きして、必要なら、子供を守るために先生を遠ざける行動も必要になります。子供を守るのが一番大切です。)
また、学校の方針、先生、友達、カリキュラム、学習進度、部活、行事などできるだけ関心を持っておくのは大事です。そういう会話を親子でできるとよいですね。
親が、学校の先生を尊敬し、学習内容に関心を持っているということは、子供に伝わると、子供も先生を尊敬し、勉強内容に興味を持つことにつながります。
親から先生を軽んじる話はしないほうがいいですが、子供が先生についてすごく困っているいやな気持になるようなことは聞いてあげる必要はあります。子供に害があるような、先生についての悩みもありえます。
先生にもいろんな方がいるので、困った面が目に付いたり、場合によってはもっとよくないケースもあります。そういう場合も早めに気づいてあげて、お子さんを守るためのアクションができるとよいと思います。塾と違って、公立の中学は通常先生を変えられませんけれど、改善方法を探れるかもしれません。
先生ご本人と親が相談してかかわり方を工夫してもらったり、学年主任、教頭、校長などの上司の先生方や教育委員会に相談して、ほかの先生たちのフォローを受けられるようにしたり。緊急度が高い場合は、とりあえず、休ませて自宅学習にしたり、学区外への転校を考えたりなどお子さんを守る手立てをする必要があります。

【3】子供の学力を知る
まずは、普段の通知表、定期テスト、学力テストのほか、模試や塾のテストなどから、全体的な学力レベルを把握します。
得意不得意教科を知り、中でも、遅れている苦手な部分をピックアップしていきます。
・計算の中でも分数が苦手。
・数学好きだけど図形だけ嫌う。
・理科の生物は好きだけと物理的なところだけ苦手。
・英語文法があやふや。
などがあると思います。また、小学校時代も振りかえって、たとえば小3までは80-90点とれてたのに小4くらいからカラーテストの点が70点とか増えた…なども思い返してみます。
教科の得意不得意と合わせて、単元ごとの習熟度も凸凹があるはずなので、どこが抜けているのかなども把握したいです。
ちょっと大変ですが、学校の先生、できれば、担任の先生のほか、5教科の教科ごとの先生に、お子さんの弱い部分、復習すべき部分や今後の勉強の仕方を面談や電話で教えてもらうことができると、よいと思います。
過去1~2年のテスト答案を振り返って、苦手個所を洗い出すこともできます。
そのほか、塾や通信教育を検討しているなら、そのサービスの中で学力診断テストを受け、苦手個所の洗い出しや今後の勉強の提案を受けることもできます。
【4】高校について知る
子供が通う可能性のある高校をできるだけいろいろな学校を親が知っておくとよいと思います。
詳しく知ると意外な魅力があったり、お子さんに合いそうな内容の高校が見つかったりもするので、あまり最初から絞り込まないほうがいいと思います。
まずはご近所で名前を見聞きする高校のホームページをのぞいてみるのもいいですね。資料請求方法や学校説明会の案内などもみることができます。
塾予備校、新聞社出版社、自治体や公的団体などが主催で、高校中学の合同学校説明会、入試相談会、私学フェアなどをやっていたりするので、そういう入試情報イベントでいくつかのブースで資料をもらって説明を聞き、実際に高校見学する学校を絞り込むのもおすすめです。各高校でのオープンキャンパスや説明会など見学もいくつかしてみましょう。
できれば親子で行くのがいいですが、お子さんがまだ乗り気でないとかスケジュールが合わないなら親御さんだけでもいってみるとよいと思います。
・高校からの進路、進学実績
・大学入試について国立大私立大の「一般選抜」に対応する指導はあるか
・大学入試について「学校推薦型選抜」「総合型選抜」についての手厚いフォローや学校枠があるか
・学校の授業や学習指導は子供のレベルに合っているか。手厚いフォローがあるか。
・子供の希望する部活や学校活動、イベントがあるか
・子供にとって魅力あるカリキュラムになっているか
・先生と話しやすい雰囲気があるか
・校舎施設は教育面のほか、ロッカーの有無、トイレなど安全衛生面なども問題ないか
・学食・売店の有無や使用状況
また、塾に通っている場合は、地元の公立私立の高校との情報交換に力を入れ入試情報に強い塾もあります。高校別の入試対策ノウハウがあったり、独自の偏差値レベル表なども作っていたりして、そういう塾からの情報も役立つことも多いです。
【5】入試 受験状況を知る
高校大学入試は、年々変化があります。私は娘が二人いますが、上の子と下の子で数年の間にいろいろ変化がありました。今後も各自治体、各校で試行錯誤しながら入試は変化していくと思われます。
また、公立私立ともに、都道府県ごとに制度や通例になっている常識などが違うので、通いたい高校のある自治体の高校入試情報を知る必要があります。
出願方法、入試方式や時期、入試科目や試験内容傾向、英検など検定資格の有利性、まわし合格制度(一度の入試で二つ以上の学校や学科に出願し合格する可能性がある)、定員の増減、学科の変更、など、重要なものは中学校からも情報提供があるはずですが、日ごろから新しい入試情報には敏感になっておくとよいでしょう。
【6】塾、通信教育、家庭教師など学習サービスを知る
おおまかに、家庭学習をすすめるためには、個人で市販教材を買って各自で進める以外では、以下のような学習サービスを使うことが多いです。
対面型は比較的高額になりがちですが、実際に毎週塾の校舎に足を運んで授業を受けることで、学習を続けやすい面はあると思います。
ただ、オンラインの学習サービスも、学習継続のシステムや子供や保護者へのフォローが手厚いものもあります。費用も様々ですが、たとえば、地方の中学生が東大の学生家庭教師に習うことも可能になっていて、目的やお子さんのタイプ、予算など、いろいろな条件に照らして選ぶことが可能です。
集団塾に通いながら、オンライン家庭教師も併用するなど、学習サービスを組み合わせて利用することもよく聞きます。
対面型の塾、家庭教師
・集団授業タイプの塾
・個別指導タイプの塾
・家庭訪問型の家庭教師
オンラインの塾、通信教育
・動画授業受講タイプ
・双方向コミュニケーション学習サービス
・一対一の個別指導や家庭教師
その他
・紙教材を使用した通信教育など
まとめ
情報編~子供の成績アップのために親が知ることについては、以下の6ポイントをご紹介しました。
一度に何もかもわかることはもちろんないので、普段から意識してだんだん必要な情報に触れ活用していくことが大事です。
【1】子供を知る、親が自分を知る
【2】学校を知る
【3】子供の学力を知る
【4】高校について知る
【5】入試 受験状況を知る
【6】塾、通信教育、家庭教師など学習サービスを知る